・固定金利は無駄だと思う変動選択者 ・変動金利は怖いと思う固定選択者
による討論スレッドです。
金利差額や余剰資金を繰り上げに回すか、運用に回すかなどなどの討論もどうぞ。
[スレ作成日時]2014-03-08 16:31:48
注文住宅のオンライン相談
固定金利は無駄じゃない? 変動金利は怖くない?【Part 5】
|
27:
匿名さん
[2014-03-09 08:40:55]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
||
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報





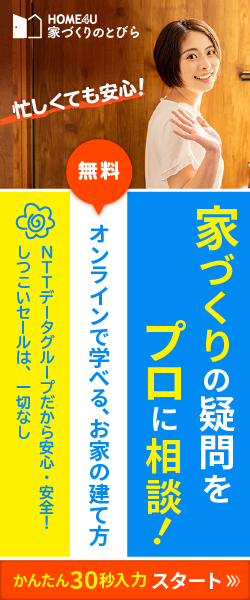

アングル:「変動型」に傾斜する住宅ローン、反転リスクに警戒感も 2012年 12月 14日
[東京 14日 ロイター]住宅ローン市場で「変動金利型」の残高が増加している。銀行による利用者の獲得競争が激化し、貸出金利が下がって手ごろ感が出ている一方、金利は当面上がらないとの見方が利用者に広がってきたためだ。
しかし変動型には、もとになる市場金利が反転上昇したときに返済が滞りやすくなるリスクがあり、金融庁は変動型に傾斜する住宅ローン市場に警戒感を強めている。
「これなら無理なく返済できそうだ。決めます」──。固定金利に基づく返済プランを見て住宅購入に難色を示していた見込み客が、月々の返済額がより低額となる変動金利型のプランを見て購入を決めるケースは珍しくないと、都内の不動産業者は話す。
法人の資金需要が見込めない中で、銀行は有力な貸出先確保のため住宅ローンの金利引き下げ競争を激化させている。主に短期金利をもとにする変動型ローンの金利は最優遇で0.7─0.8%台と、今や「採算割れスレスレ」(主要行幹部)まで低下している。長期金利の固定型も借入期間21年以上35年以下で1.8%台と過去最低水準だが「利用者は1%の差は大きいと捉えている」と、別の不動産業者は言う。住宅ローンの利用予定者を対象に住宅金融支援機構が実施のアンケートでは、固定金利型を検討していた人が4─5割のところ、実際の利用は2割程度にとどまっている。
住宅ローン市場はここ10年、残高ベースで170兆─180兆円の間を横ばいで推移してきた。しかし、内訳は大きく変化している。固定型と変動型の明確な切り分けは難しいが、金利を数年間固定した後で変動に移行するタイプを含めた変動型を大多数扱っている銀行や信金、農協による貸し出しは、右肩上がりに増え、市場全体に占める割合は2001年の6割が11年には8割強へと拡大した。半面、全期間固定型を手掛ける住宅金融支援機構の割合は、01年の3割強が11年には1割強にまで縮小した。
<「変動金利リスクの蓄積、サブプライム問題の一因」>
住宅ローン市場のこうした状況に、金融庁は警戒感を強めている。市場金利が低位安定している今は、固定型より変動型に利用者の目は向きがちだが、反転上昇すれば変動型での月々返済額は当然増える。複数の金融庁幹部は「米国でサブプライムローン問題が深刻化したのは、金利の変動リスクが蓄積されたことも一因だ」と、指摘する。
世界の住宅ローン事情に詳しい住宅金融支援機構調査部の小林正宏主席研究員(海外市場担当)によると、住宅バブルに沸いた2000年代初頭の米国では、過去に延滞履歴があるなど信用度の低い「サブプライム層」を中心に、借り入れ当初の月々返済額が手ごろだった変動金利型への人気が集まった。その後の金利上昇で月々返済額が跳ね上がったのに加え、不動産価格が下落し、転売や借り換えができなくなり返済不能に陥る借り手が相次いだ。
日本とアメリカでは、事情が異なる面も多い。米国では信用度の低い借り手にまで貸し出したことが危機を深刻化させたが、日本の場合、収入証明を要求するなど返済能力を厳しく見ている。金利が上昇したとしても返済可能かどうかをストレステストを通じて確認するのも一般的だ。不動産バブルがあった米国と違い、日本では不動産価格が長期低迷しているため、現在以上に担保価値が著しく低下する恐れも少ない。健康保険などのセーフティネットもあるため、急な医療支出が家計を圧迫する米国に比べ返済余力は相対的に安定しているとされる。
しかし日銀は、住宅ローンを抱える家計について「所得対比でみた債務の元利返済額の比率が引き続き高めとなっており、債務返済負担に大きな改善はみられていない」(金融システムレポート10月号)と指摘。金融庁の幹部は「景気回復を伴わない金利上昇があれば、変動型の利用者の返済が滞りかねないリスクは日本も同じだ」と話す。
日銀は当面、物価上昇率が1%になるまでは金融緩和を推進する構えだが、一般的に住宅ローンの返済期間は20─35年と長期にわたる。変動型で金利の低い当初の2─3年分を返済しただけでは、残高はほとんど減らない。通常は長期金利の方が立ち上がりが早いため、金利が上昇し始めてから固定型へ借り換えるのは現実的に難しいとの見方が一般的だ。
<金融庁は審査体制の監視を強化>
個人にとって住宅は、一生に1度購入するかどうかの高額商品のため、経験を通じた学習効果が得られにくい。小林氏によれば、米国では住宅価格が上昇し続けるから金利が上昇しても借り換えや物件処分で対応できると安易に借りていた面があるとされる。一方、今の日本の住宅ローン利用者は「金利上昇のリスクは気にしていても、当面は上昇しないとの思い込みも根強い」と、複数の不動産業者は指摘する。
変動型では、金利が変動するリスクを負うのは利用者側だ。ただ、これが貸し倒れにつながれば銀行経営にも影響を及ぼしかねない。日銀の統計に基づくと、銀行の融資に占める住宅ローンの比率は、2001年度末の約15%が11年度末には約25%にまで高まってきている。バークレイズ・キャピタル証券の田村晋一アナリストは「短期金利の2%程度への上昇なら織り込み済みの銀行が多いが、急激な3─4%以上への上昇があれば、ローンの貸し倒れや返済猶予などへの対応を迫られる銀行が出る可能性がある」と見ている。
金融庁はこのところ、金融機関における金利リスクの管理体制の点検に力を入れている。住宅ローンについては「各利用者の信用度に応じた金利を設定しているなら問題ない」(幹部)との認識だ。米サブプライム問題では、銀行が債権を証券化し外部に切り出したことで、審査上のモラルハザードを招いたとされる。しかし日本では、住宅金融支援機構が買い取る固定型以外は銀行がリスクを抱え込むため「審査を甘くするとは考えにくい」(別の幹部)と見ている。
とはいえ銀行にとって住宅ローンは、教育ローンや資産運用などのサービスにつながる「入口」の役割も持つため、にわかに競争から手を引くわけにはいかない。特に激戦区の3大都市圏では「審査を甘くしてでも顧客を得ようとする金融機関がいつ出てきてもおかしくない」と、銀行関係者らは話す。金融庁は「リスク軽視のダンピング競争になるなら看過できない」(同)と、ローン審査体制の監視を強める方針だ。