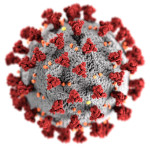第18回 名誉毀損の成立阻却事由(3)

今回も、前回までに引き続き、名誉毀損の成立阻却事由(免責要件)を取り扱います。
民事における名誉毀損(不法行為)に関し、形式的には名誉毀損に当たる表現であっても一定の要件を満たす場合に名誉毀損に当たらないとされる真実性・相当性の法理について、今回は、相当性の法理を詳しく見ていきます。
1相当性の法理の要件
相当性の法理について、判例は「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、(中略)もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当」(最判昭41・6・23民集20-5-1118)と述べています。
なお、判例は意見・論評による名誉毀損について、「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべき」(最判平9・9・9民集51-8-3804)と述べて真実性の法理の適用を認めていますが、「仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当」(同判決)として、相当性の法理の適用も認めています。
上記から、相当性の法理の要件は、①公共の利害に関する事実であること、②もっぱら公益を図る目的であること、③事実が真実であると信じることに相当の理由があることの3つに整理され、このうち①、②については、真実性の法理と共通ということになります。
2相当性の法理の趣旨
前回までに見たように、公共性、公益性が認められる表現行為については、それにより他者の社会的評価が低下し名誉が毀損されても、摘示された事実が真実であることが証明されれば、真実性の法理が適用されて不法行為責任を負うことはありません。
しかし、表現行為にかかる事実が真実であることを証明することは簡単なことではなく、もし真実であることが証明できなければ不法行為責任を負うということになれば、マスコミが公共性のある重要な事実についても報道を控えるなど、萎縮効果が生まれると考えられ、国民が必要な情報を得る機会が失われ、知る権利が害されるおそれがあります。
そこで、真実性に関する裏付け調査を行うなど、相当な手段を尽くして行った表現行為については、結果的に真実性が認められなくても、その責任を問わないという扱いがされていると考えられます。
3相当性の判断の基準時、判断基準
相当性の判断の基準時について、判例は「摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由が行為者に認められるかどうかについて判断する際には、名誉毀損行為当時における行為者の認識内容が問題になるため、行為時に存在した資料に基づいて検討することが必要」(最判平14・1・29判時1778-49)と述べ、事実審の口頭弁論終結時とする真実性の判断基準時とは異なる時点をとっています。事実が客観的に真実であるかどうかではなく、真実であると信じたことの相当性が問われますので、事実と信じて表現行為を行った時点が基準とされることになります。
また、相当性が認められるかの判断については明確な基準があるわけではなく、それぞれの事案における情報源、裏付け資料、資料の入手方法等の様々な事情を総合的に考慮して判断されます。この点の判断が問題となった代表的なケースについては、次回にご紹介します。
相当性の法理の要件は、①公共の利害に関する事実であること、②もっぱら公益を図る目的であること、③事実が真実であると信じることに相当の理由があることの3つであり、①、②は、真実性の法理と共通する。
相当性の法理は事実の摘示による名誉毀損のみではなく、意見・論評による名誉毀損についても適用され、その場合には意見、論評の前提となる事実の重要部分について真実と信じたことの相当性により判断される。
相当性の判断は、名誉毀損行為当時が基準時とされる。
相当性が認められるかどうかは、個別の事案における情報源、裏付け資料、資料の入手方法等の事情を総合的に考慮して判断される。
次回は名誉毀損の成立阻却事由が争われた具体的なケースを見ていきます。
 このコラムの執筆者
このコラムの執筆者原田真(ハラダマコト)
一橋大学経済学部卒。株式会社村田製作所企画部等で実務経験を積み、一橋大学法科大学院、東京丸の内法律事務所を経て、2015年にアクセス総合法律事務所を開所。
第二東京弁護士会所属。東京三弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会副委員長、同高齢者・障害者の権利に関する委員会副委員長ほか
コラムバックナンバー
- 第46回 住宅(不動産)にかかわる民法改正の概要(1)

- 第45回 プライバシー侵害の救済方法(7)

- 第44回 プライバシー侵害の救済方法(6)

- 第43回 プライバシー侵害の救済方法(5)

- 第42回 プライバシー侵害の救済方法(4)

- 第41回 プライバシー侵害の救済方法(3)

- 第40回 プライバシー侵害の救済方法(2)

- 第39回 プライバシー侵害の救済方法(1)

- 第38回 プライバシー侵害の成立要件(5)

- 第37回 プライバシー侵害の成立要件(4)

- 第36回 プライバシー侵害の成立要件(3)

- 第35回 プライバシー侵害の成立要件(2)

- 第34回 プライバシー侵害の成立要件(1)

- 第33回 名誉毀損の救済方法(12)

- 第32回 名誉毀損の救済方法(11)

- 第31回 名誉毀損の救済方法(10)

- 第30 名誉毀損の救済方法(9)

- 第29回 名誉毀損の救済方法(8)

- 第28回 名誉毀損の救済方法(7)

- 第27回 名誉毀損の救済方法(6)

- 第26回 名誉毀損の救済方法(5)

- 第25回 名誉毀損の救済方法(4)

- 第24回 名誉毀損の救済方法(3)

- 第23回 名誉毀損の救済方法(2)

- 第22回 名誉毀損の救済方法(1)

- 第21回 名誉毀損の成立阻却事由(6)

- 第20回 名誉毀損の成立阻却事由(5)

- 第19回 名誉毀損の成立阻却事由(4)

- 第18回 名誉毀損の成立阻却事由(3)

- 第17回 名誉毀損の成立阻却事由(2)

- 第16回 名誉毀損の成立阻却事由(1)

- 第15回 名誉毀損の成立要件(4)

- 第14回 名誉毀損の成立要件(3)

- 第13回 名誉毀損の成立要件(2)

- 第12回 名誉毀損の成立要件(1)

- 第11回 近隣紛争(2)

- 第10回 近隣紛争

- 第9回 住宅の相続に関する問題

- 第8回 土地の境界に関する問題

- 第7回 建物建築工事契約の留意点

- 第6回 建物の建築が制限されるケース

- 第5回 不動産登記の基礎の基礎

- 第4回 法的観点からみる住宅ローン

- 第3回 売買契約締結後のトラブル(2)

- 第2回 売買契約締結後のトラブル(1)

- 第1回 住宅、土地の購入と契約の解消